OME 各種メディアへの掲載・出演 2009年 7月11日「世の中には必ず『特例がある』投資信託の損は取り戻せる」(週刊現代)
週刊現代にコメントが掲載されました(2009/7/11号)
世の中には必ず「特例がある」

 タイトル 投資信託の損は取り戻せる(P32~34)
タイトル 投資信託の損は取り戻せる(P32~34)
高齢者の資産を狙い撃ち
東京23区内に住む女性Tさん(80歳・無職)は亡夫に対する申し訳ない気持ちが募り、最近、満足に眠ることができない。夫の遺してくれた資産が、わけのわからないうちになくなってしまったからだ。
出入りの証券マンにダマされて巨額の投資信託を購入し、それらが紙クズ同然になってしまったのだ。
3年前に夫を亡くし、そのとき彼女の手元に残ったのは保険金などを合わせた4000万円。
当初はこれを日本国債で運用していたが、その後、証券会社に勧められるままに投資信託に乗り換えた。新興国の「公社債ファンド」や米国の「ハイ・イールド債権ファンド」など聞いたこともない投資信託を次々に売買され、聞いたこともない投資信託を次々に売買させられ、最終的に資産のすべてがハイリスクの投資に化けた。やがてそれらは、昨年のサブプライム問題をきっかけに暴落。損害額は3000万円にまで膨れ上がった。ファンドはどれも先物やデリバティブを組み合わせた複雑なもので、80歳の高齢者が理解できるものではない。証券会社の営業マンは、同居する息子夫婦が家を空ける平日の日中を狙って現れるのが常だった。話し相手にもなってくれる営業マンに「資産運用」のためと言われ、サインと押印を繰り返した。「このような事例であれば、金融機関側の違法性が認定され可能性は高いと考えられます。投資信託を何度も乗り換えさせる手法は、金融機関側が手数料を稼ぐためだと推認される事情となるからです」と金融取引のトラブルに詳しい本杉明義弁護士は語る。同弁護士によると、銀行から投資信託の購入を勧誘された高齢者のトラブルが増えてきたという。ありていにいえば、一部の投資信託は高齢者をカモにして販売実績を伸ばしてきた。そんな卑劣な商売に、銀行やゆうちょが手を染めるようになっている。「銀行の顧客というのは元々定期貯金ぐらいしか投資経験がない人が多い。そういう人に対して、銀行は『貯金の延長のようなものですよ』と言って満期になった定期貯金をリスクのある投資信託に振り替える営業をしたわけです。確かに顧客にも定期貯金ではほとんど利息がつかないといった不満があったわけですが、だからといってリスクの高い金融商品やデリバティブの入った複雑な内容の投資信託を販売しても良いという理由になりません」(同弁護士)じつはいま、こうしたトラブルから訴訟沙汰となり、金融機関が顧客に損害の一部返還するケースが増えているのである。投資でいくら損をしようと、それは投資家の自己責任であるのは言うまでもない。ただし、それは投資家が何に投資しているかを理解している場合に限る。金融機関の売り方に問題があれば、話しは別だ。
訴訟よりも手軽なあっせん
金融商品取引法では、顧客の実情に照らした販売を行う「適合性の原則」が義務づけられている。具体的には、1.顧客の財産状況、2.知識と経験、3.意向の3つに照らして適切な商品以外は売ってはならない。したがって、冒頭の80歳女性のケースのように大切な老後資金をリスクの高い投信に振り向けるのは、適合性の原則からいって大いに問題があるのだ。ファイナンシャルプランナーの紀平正幸氏はこう指摘する。「裁判所の判断をみると商品への理解度も重要です。たとえばレバレッジをかけたものなど仕組みが複雑な商品は、われわれ専門家が目論見書を読んでも理解に苦労することがある。そういう商品を投資経験の乏しい80歳の顧客に売った場合、それだけで問題だといわざるをえません」一般には自分でサインをした以上、相手に非を求めることはできないと考えがちだが、じつはそうとは限らない。前出の本杉弁護士がこう説明する。「かつて裁判所は顧客のサインがあれば商品を理解したものと見なしていました。しかし、いまは売った側がどう説明し、それをその顧客がどこまで理解したかで判断するよになっています。ですから、一人暮らしの高齢者に複雑な商品を売った場合、金融機関がいくら「説明してサインもある」と主張しても、裁判所が客観的にみて理解できたとは思えないと判断する可能性があるわけです」こうなると、売る側との会話にやりとりが重要になってくる。そこで、「金融機関との会話を録音するか、メモを残しておくだけでも、トラブルになったとき証拠として認められる可能性があります」(前出・紀平氏)もっとも訴訟となると、時間も費用も要し、それなりに腹を据えてかからなくてはならない。それに費やした労力に見合っただけのものが取り戻せるかも少々疑問だ。そこで勧めたいのが、日本証券業協会が行っている「あっせん」という制度である。日本証券業協会では古くから顧客の苦情処理を受付ていたが、96年以降、第三者である弁護士の協力を得て、顧客と金融機関のトラブルの仲裁、解決に乗り出すようになった。まず顧客からの苦情や相談を受けた「証券あっせん・相談センター」が金融機関に対して苦情の取次ぎや事実関係の調査を指示。これに対して金融機関には調査報告の義務があり、その結果を踏まえて、センターは相談者である顧客に解決策の助言を行う。これで問題が解決すればいいが、不調に終わった場合、顧客は所定内容を書いて提出し、あっせんを申し立てが受理されると、センターは協会に登録されている弁護士を「あっせん委員」に任命。あっせん委員は、顧客と金融機関の双方の言い分を聞いて和解案を提示する。同センターによると、08年度の苦情の総件数が966件で、あっせんの申し立てに至ったのは278件。このうち和解が成立したのは、ほぼ半分の132件だ。「例年、あっせんの新規申し立て件数は150件前後で推移していましたが、昨年度は278件と急増しました。とくに下半期の伸びが大きく、やはり株価の下落で金融商品の損が拡大した結果、相談件数も急増したものと思われます」(金子得栄所長)。
損失の80%が返ってきた!
あっせんでは、弁護士立会いのもとで顧客と金融機関の両者が出席する場がもたれる。「話し合いの場が平均2~3回もたれ、その間は3ケ月ほどです。この制度はあくまでも話し合いの解決をめざしており、お互いが歩み寄ればいいのですが、双方の意見の想違があまりに大きい場合は、1回で不調に終わることもあります」(同所長)メリットは簡易性と迅速性だ。裁判のような煩雑な手続きはなく、しかも1年、2年と長引かずに数ヶ月で決着がつくことが多い。金融機関としても、時間と労力のかさむ裁判よりも、あっせんで早期に決着をつけたほうがありがたいというのが本音のようだ。「あっせんのもう1つのメリットは専門性の高さです。通常の裁判官は法律の専門家であって、金融商品の専門家ではありません。しかし、われわれの相談員は金融商品に詳しいその道のプロですし、担当弁護士も専門知識の豊富な人たちです。それだけに顧客の実情に即した判断ができると考えています」(同所長)ちなみに和解額については、ケースバイケース。最近の具体的ないくつか拾ってみよう。いずれも今年に入ってから和解が成立したケースだ。
・投資信託で340万円の損失を出した男性(70歳)勧誘の際、金融機関からリスクについての詳しい説明がなく一方的に損をしたとして、あっせんを申し立てた。金融期間側は詳しい説明を行ったと主張したが、担当委員は「勧誘にあたり、男性と直接面接をしておらず、リスクについて十分に説明した事実はない」として、金融機関の言い分を退け、結局272万円の支払いで和解成立。
・高齢の母親に十分な説明のないまま投信を購入させ、損失をまねいたとして息子(49歳)が申し立て。母親は定期貯金のつもりで投信を買ったとして損失分700万円の損害賠償を求めた。担当委員は、男性が投信購入の事実を知ってから取引無効を主張する機会があったののに、損失が出てから苦情を申し立てたことには過失があるとした。しかし、金融機関側の対応にも不十分な点があるとして、215万円を支払うことで和解が成立した。
・軽度の認知症を患う男性(77歳)が、リスクの説明がないまま定期貯金を解約させられ投資信託を買わされたと、損失分150万円の損害賠償を請求。担当委員は男性の言い分を認める一方、「判断能力が全くないとはいえない」として、88万円の支払いで和解。高齢者のケースが多いが、そうでなくても金融機関側の不手際によって損失を破った場合、ある程度損失を取り戻す事は可能なのだ。泣き寝入りするなどもってのほか、「馬鹿なことをした」と自分を責める前に、すべきことはある。


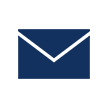 でのお問い合わせは
でのお問い合わせは










